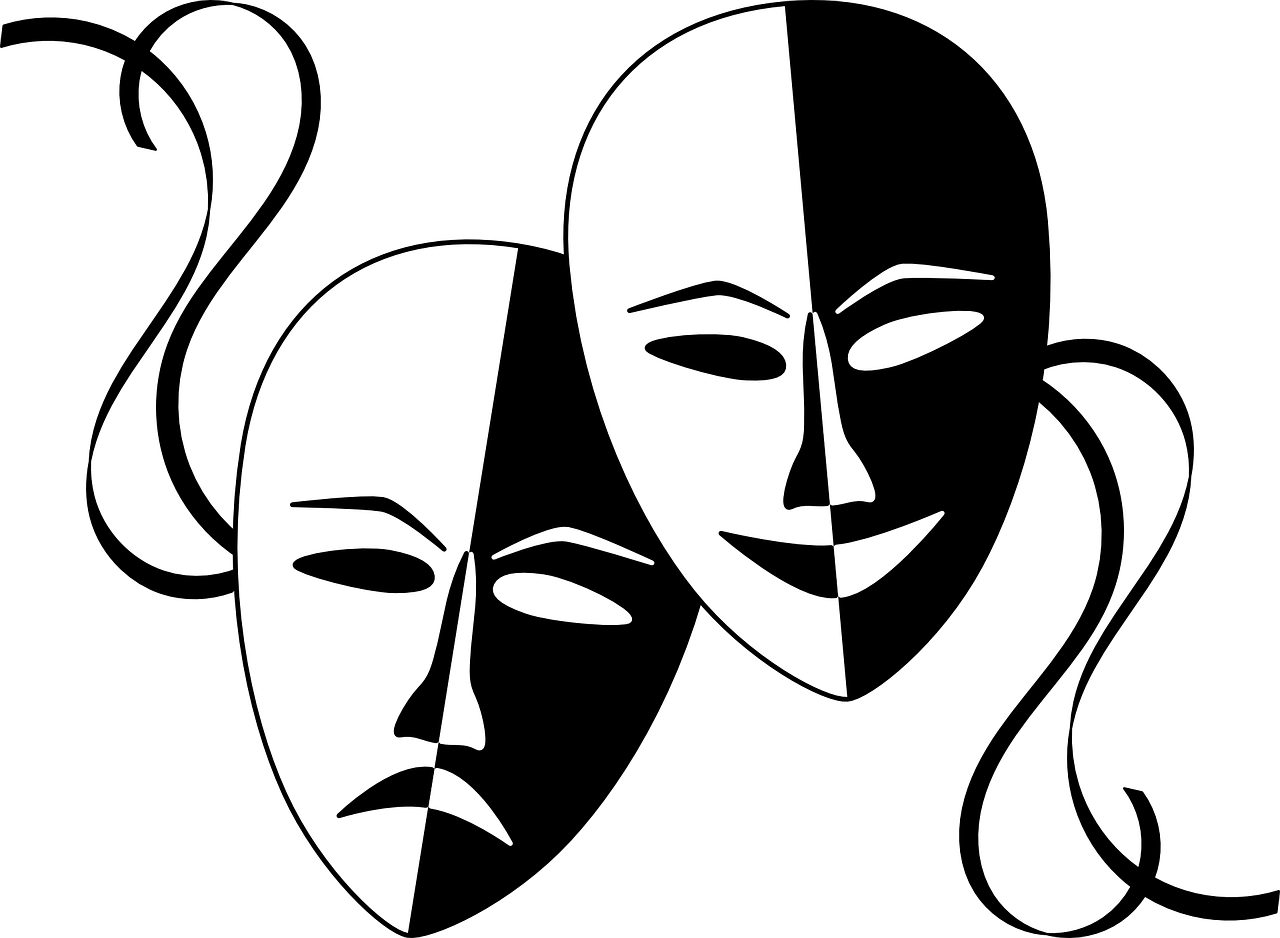
目次
吉野勝秀のような俳優のタイプについて考える
ひとくちに俳優と言っても、さまざまなタイプの人がいます。
泣く演技が自然な人や長い台詞を流暢にしゃべる人など、得意としていることは千差万別です。
それぞれ特色を持っていますが、演じ方によって大きく2種類に分けられます。
【役になりきるタイプ】
1つ目は役になりきるタイプです。
監督の指示通りに演じることを何よりも大切に考えています。
台本を読み込んで頭の中で自分が演じる登場人物像を明確にして、その人になりきるために徹底的なシミュレーションを行うのです。
言い換えると自分の個性を主張しないどころか、徹底的に消すことによって役になりきろうとしています。
それが上手くいけば、世間での評価はいろんな役をこなせる多彩な役者ということになるでしょう。
監督も使いやすいと感じることが多く、次々といろいろな依頼が舞い込んでくることになります。
1つだけ問題があるとすれば、個性派の役者の陰に隠れやすいことが挙げられます。
いくら役を演じるのが上手でも印象に残りにくいことが多いからです。
印象に残りにくいのは、必ずしも悪いことではありません。
役によって与える印象が変わるほど、上手く演じ分けているといえます。
つまり印象に残らないのは演技力の裏返しといっても過言ではないです。
そのためテレビなどで紹介されるときは、代表作について語られるのではなく演じた役の数が話題になることが多いです。
【自分の個性を強烈に活かして演じるタイプ】
2つ目は吉野勝秀のように自分の個性を強烈に活かして演じるタイプです。
このタイプはどのような役を担当するときも、演じ方に大きな違いがありません。
そのため演技力の評価は高くないことも珍しくないです。
たしかに演技が下手であることが理由で、演じ分けられていない人もいます。
事務所の方針で強引にキャスティングされているアイドルなどに、そのような傾向が見受けられます。
しかし演技力がある俳優であっても、個性を活かして演じていることが理由で、どの役でも同じに見える人もいます。
モノマネされることが多いことからも分かるように、視聴者はその特徴を強烈に印象付けられているのです。
その個性を嫌う人には受け付けてもらえないリスクがありますが、一般的には視聴率を取りやすくなるメリットのほうが大きいです。
その個性が多くの人を引き付けることを知っているから、どのドラマでも活かそうとしているということです。
つまり吉野勝秀のように俳優として自分を磨いていく過程で、魅了しやすい演じ方がスキルとして身に付いたと考えられます。
視聴者はその演技を期待して見ていることが多いため、演じ分けないことが不満につながることは少ないです。
(参考):俳優・吉野勝秀についてのまとめ
声優をイメージすれば分かりやすいのでイメージしてみてください。
どのキャラを演じるときでも声は一緒なのに、代表的なキャラがたくさんある声優は珍しくありません。
視聴者はその声が好きなのであり、いつも一緒だからといって不満を持つことは少ないです。
それと同じで俳優も必ずしも演じ分ける必要があるとは言えません。
主役クラスを後者にして脇役を前者で固めることになりやすい
このように個性を消すタイプと活かすタイプがあり、人によってどちらを高く評価するのか異なります。
前者ばかりだと味気ない作品になりやすいですし、後者ばかりだと既視感の漂う作品になるでしょう。
したがって、両者をバランス良くキャスティングしているのが理想的であると考えられます。
そうなると自然と主役クラスを後者にして、脇役を前者で固めることになりやすいです。
キャスティングを逆にしてしまうと、主役クラスの存在感が薄くなってしまう恐れがあるからです。
とはいえ、常にそのセオリーが当てはまるとは限りません。
実際は監督をはじめとしたスタッフがバランスを考えて人選することになりますし、指導によって演じ方を矯正してもらうケースもありえます。
年配の俳優の場合は演じ方が染み込んでいて、あまり指導に従ってくれないことも多いです。
若い場合も性格によっては聞き入れてくれないケースも見受けられます。
どちらにせよ俳優を上手く活かすために、監督やその他のスタッフは試行錯誤を繰り返すのが一般的です。
現場で信頼関係が築かれることによって、指導をしっかり聞き入れてもらいやすくなります。
職人気質の人と社交性のある人に分類することもできる
他にも、いろいろなタイプの分け方があります。
たとえば、職人気質の人と社交性のある人に分類することも可能です。
前者はあまり世間話をしないことや、納得できるまで演技を繰り返すことが特徴として挙げられます。
下手な後輩や手際が悪いスタッフを叱ることも少なくありません。
一方で後者は、撮影以外の時間も大切にしており、場の雰囲気を盛り上げることを大切に考えています。
現場に来るときに差し入れをしたり新人を誘って食事に行ったりするなど、ムードメーカーとしての役割も大きいです。
そう言われると、後者の方がありがたい存在であるように感じるでしょう。
しかし前者のようなタイプがいないと、現場が引き締まらないのも事実です。
このように、どのような分け方をしたときでも、一方に偏っている状態は良くありません。
最終更新日 2025年12月24日









